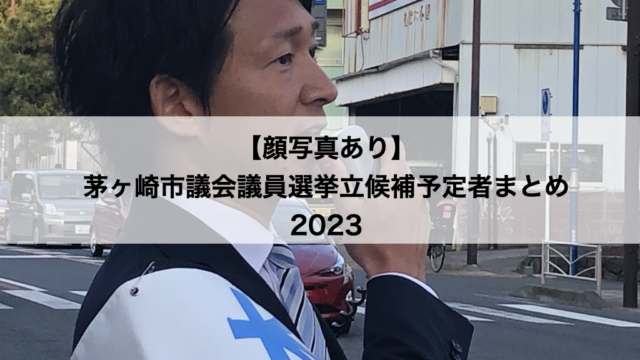昨日の朝は茅ヶ崎駅南口西側からスタートしました。
たくさんの方々からお声がけいただき、活動誌も予想以上に受けとっていただきました、ありがとうございます!
その後は市役所4Fにて開催されました子育て講座に参加し、「イヤイヤ期の子どもの心に寄り添う」ことをテーマとした講義を拝聴したしました。
うちの上の子が2歳ちょっとで、まさにイヤイヤ期なんですよ。
夫婦共々なかなか子育てに手を焼いている真っ最中でもあり、当事者としても講義を聞いておりました。
書籍やネットの記事に載っている情報ってまさに正論で、「そうした方がいい」なんて誰もがわかっていると思います。わかっていてもなかなか余裕が無くて実践できないのが「子育て」の難しいところだと思います。
講師である坂上裕子氏(青山学院大学准教授)はご自分の体験談や、場面場面での親の心情なども引き合いにとてもわかりやすく説明しておられました。
特に面白かったのが、子育てのゴールは「自立」と「自律」であり、その育ちの過程を車の運転に例えられていたことです。
運転する時って、行き先やルートを決めて、それに向かってアクセルとブレーキを駆使しながら目的地に向かいますよね?
子どもはまず「アクセル」にあたる、「面白い・楽しい」といった感情や好奇心、いろいろなことに挑戦したくなる気持ちが先行します。
そのアクセルの育ちに少し遅れて「ブレーキ」にあたる、「考える力・言葉を扱う力・自分の感情や行動をコントロールする力」が遅れて育ってきます。
ですからかんしゃくを起こすのはごくごく自然なことであり、
大切なのは
イヤイヤを無くすことではなく、
かんしゃくを起こさせないことでもなく、
「アクセル」の育ちも大切にしながら「ブレーキ」の育ちを支えていくことだそうです。
では「ブレーキの育ち」を支えるには???
●そもそも子どもはどうしてイヤイヤするのか?
・自分で感情をコントロールすることが難しい
・ことばで自分の思いを伝えられない。
・先の見通しをもてない
・自分で気持ちを切り替えるのが難しい
●感情が暴発しているときに必要なこと
→「安心」させてもらうこと
方法としては
①思いを受け止める(思いを言葉にしてあげる)
「〜したかったね」「悲しかったね」「〜できなくて怒ってるの」
→「わかってもらえた」と安心する
②行動の枠を示す
親が「だめ」を通してよいこと
自分の命や健康に害を与えること・人に害を与えること(社会のルール)
この枠を、おとながきちんと示してくれるから、子どもは安心して行動できる
大事なのは子どもの思いを認め、受け止めることと、それを行動として認めることは別だと認識することだそうです。
③見通しを示す
・子どもがアクセルを踏み続ける時:先の見通しが持てないから
→おとなが具体的に見通しを伝える
「これをやったら、それやろうか」「10秒待って」「今はダメだけれど、〇〇になったらしよう」
④(ことばが育ってきたら)交渉してみる
・子どもの思いを汲みつつ、親の思いも伝えて、落とし所を探る
交渉成立もあるが交渉決裂もある。あの手この手を試してみる!
大事なのは親子で対立するのではなく、困った状況に一緒に悩むこと。
「ママも困るなぁ、〇〇も困るよね、どうしよっか?」
いろんなパターンで子どもと交渉してみることが大事なんだそうです。
子どもってパパやママを困らせたいからイヤイヤしているわけじゃなく、自分の感情や伝えたいことをうまく伝えられないだけなんですね。その思いをまず受け止めてあげて、命に関わることや人に迷惑をかけるようなことであれば繰り返し注意をする。
運転も練習しないと上達しませんよね。
親が助手席に座って、行き先やルートを考えてあげて、その上でアクセル(自己主張)とブレーキ(自己抑制)を練習させてあげる。たまに補助ブレーキを踏んであげて、燃料も補給してあげる、それがまさに子育てなんですねー。
何故子どもがイヤイヤするのか?そのメカニズムがわかるだけでも、気が楽になりますし、アクセルやブレーキの教え方や、目的地の設定こそが、その家庭の子育てスタイルとなっていくということなんだと理解いたしました。
※ ※ ※ ※ ※
→【ブログ記事一覧へ戻る】
茅ヶ崎市議会議員木山こうじのSNS
木山 こうじ 41歳(無所属)

2019年の茅ヶ崎市議会議員選挙で、2,503票のご支援を頂き初当選させていただきました。
そして、この度茅ヶ崎市議会議員選挙2023でも心新たに挑戦を決意いたしました!
この4年間では、木山こうじは茅ヶ崎市議会議員として以下の点について活動してきました。
- 産前・産後ケア事業
- 茅ヶ崎市公式LINEアカウント導入
- 道路予定区域の有効活用施策
- ネーミングライツ導入
- 茅ヶ崎市長選挙と市議会議員選挙の同時実施に向け活動
- 茅ヶ崎市総合体育館、全館空調設備設置を推進
- 市内各所交差点や道路の安全対策、街灯LED化などを推進
- コロナ禍による失業者・雇用対策などを推進 など
この4年間で多くの茅ヶ崎市民の方に支えていただき、心より感謝申し上げます。
そして、今以上に茅ヶ崎市を良い街へと発展させるためにも、これからも挑戦し続けていきたいと思います!
ぜひ皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします!
→【茅ヶ崎市議会議員木山こうじはどんな人?マンガで見てみる】
茅ヶ崎市議会議員木山こうじとして、茅ヶ崎市についての情報や、日々の活動、議会や茅ヶ崎市長選挙・茅ヶ崎市議会議員選挙に関する情報などをSNSでも発信しています。
市民の皆様からのメッセージも随時受け付けておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね!

*)選挙専門大手サイト【選挙ドットコム】にも登録しています
→【選挙ドットコム 木山こうじページへはこちらから】